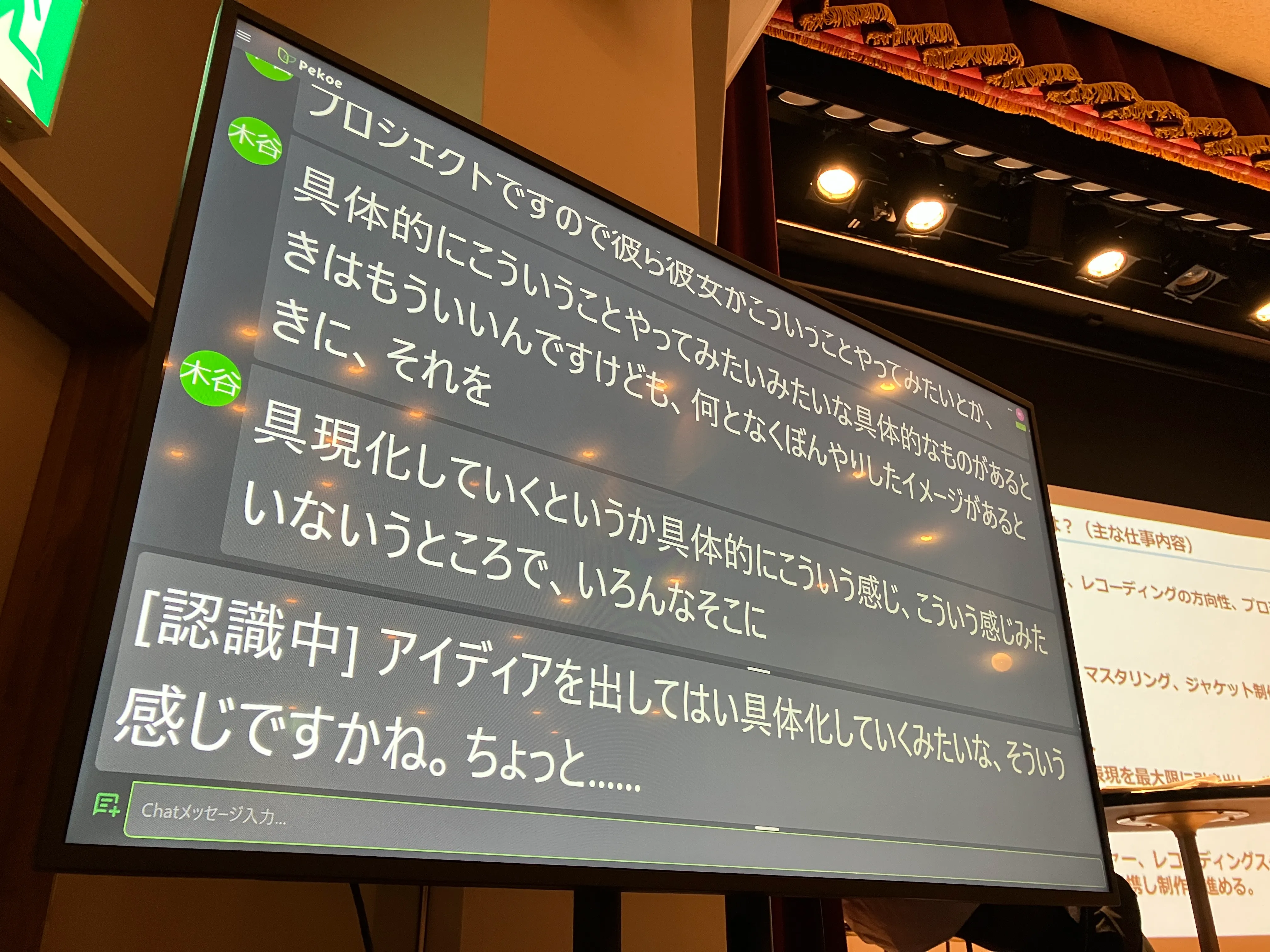Pekoeのサポートを担当している聴覚障がいを持つ当事者の木下がPekoeに関わる人たちにインタビューをしていくコーナーをスタートしました。
Pekoe(ペコ)はどのように開発されていくのか。聞いてみたシリーズ第3回はPekoeの開発を担当している、木村さん、真野さんにPekoeを起動しながらインタビューして記事にしてみました。

オンラインでのインタビュー風景(左:木下健悟。右上:真野拓郎。右下:木村純。)
インタビュアー
木下健悟:Pekoeチーム サポート担当。聴覚障がいを持つ当事者。生後まもなく薬剤により両耳とも聞こえなくなり重度用補聴器を装用している。コミュニケーション手段は口話、手話、筆談、音声認識アプリをシーンによって使い分けている
インタビューイ
木村純:Pekoeチーム 開発リーダー。リコーではプリンタードライバーの開発から始まり、PC向けユーティリティや複合機上のパネルで動作するアプリ、クラウドサービスの開発を経験。Pekoeの目指す世界に共感し、開発に参画。
真野拓郎:Pekoeチーム 開発担当。Pekoeの前身に当たるクラウドサービスを開発していたこともあり、Pekoe開発に参画。Pekoeシステムの全体構成、サーバーサイド、フロントエンドの開発を手掛ける。
– Pekoeの開発は2週間間隔で計画と実装を繰り返している
木下:
私はPekoeのサポート業務に関わるまではどのように開発に取り組んでいるのか知らなかったです。Pekoeの開発はどのように取り組まれているのでしょうか?
木村:
Pekoeとして中長期的に予定している機能と、アプリリリース後にいただくユーザーからの要望をそれぞれ検討し、スクラム(※1)という開発プロセスを活用してお客様に期待に沿う機能を2週間の間隔で少しずつ開発・リリースしています。
(※1)スクラム:短い期間で計画と実装を繰り返す、アジャイル開発のフレームワーク
木下:
お客様からの要望を2週間で検討して開発するということでしょうか。多くの要望に対しすべて開発は難しいので優先度を決めてやらないといけないと思いますが優先度はどのように決めているのでしょうか?
木村:
2週間で要望を検討して開発・リリースするわけではありません。開発を始める前に要望から求められている機能を具体化し、その機能を小分けにするなどして開発ボリュームを2週間に収める作業などの準備を行います。なので、要望を頂いてからお客様にお届け出来るまでにはもう少し多くの時間を必要とします。
また、優先度についてはお客様のお困り具合や、お客様に提供する価値の大きさ、実現容易性など様々なファクターを踏まえてチーム全体で決めています。2週間単位で計画しているので、急な要望の変更にも比較的柔軟に対応することが出来ています。
木下:
お客様の要望や声は開発チームに届いているのでしょうか?
木村:
はい。もちろん届いています。お客様と接している営業チームやサポートチームからの要望は定例会議などでチーム全体に共有されます。
また私自身、出来るだけヒアリングに参加して、技術者視点でお客様も気づいていない課題の抽出を心がけています。
– 開発者には「自ら考える」と「人に聞く」のバランスが大切
木下:
Pekoeの開発に興味を持っているひとたちが私の周りにいます。心構えやスキルなど何が必要でしょうか?
真野:
Pekoeは2週間のリリースサイクルかつ、少ないメンバーで開発を行っていますので、自主的に最後までタスクを完了させるマインドが重要だと思っています。
木村:
個人としてWebや書籍で手を動かしながら技術を学び、お客様が欲しい物が何かを自分でもしっかり考えながら最後まで作り切る実力を持ちつつ、
そのうえでみんなと協力して作るというスタイルが大切だと思います。
真野:
私も同意見で、「チームで協力して作る」、「自分で最後まで作る」といったマインドセットの話と、技術的スキルの2方向があるなと思っていて、
技術的なことは後から勉強すればなんとでもなるけど、マインドセットは木村さんが言った通りで人から言われたことをやるという人は馴染みにくいなと思います。言われたからそのまま作りますではなく、提案型の人が必要ですね。
木下:
私はすぐに人に聞いたり頼ってしまったりします。
木村:
必ずしも「すぐ聞く、頼る=悪」ではないと思います。「自ら考える」と「人に聞く」のバランスがすごく大事ということです。2週間という限られた時間で最高のパフォーマンスを出すためには自ら考えるか、人に聞くのか。人に聞けば相手の作業時間を削ってしまいチームとしての開発スピードが落ちる可能性がありますが、一方、早く目的が達成されたり、機能や実装の品質が高まったり、自分自身や周りの人の成長につながったりすることもあります。そのバランスはチームによっても違うと思うので、日々の活動の中でそれぞれが会得していくしかないのかなと思っています。
お客様からの要望から思いもしなかったことに気づいた
木下:
お客様からの要望で嬉しかったことはありますか?
真野:
考えもしなかった要望が来ることは嬉しいですね。
例えば、チャットに入れたテキストを喋らせたいという要望がありましたが、
その要望は私は思いついてなかったので、良い気付きになりました。
木下:
聞こえない人は喋るのに困っている人もいるし、議論が盛り上がっているとチャットをいれても気づいてもらえなかったりします。
木村:
私も喋れないひとはチャット入力で伝える方法で大丈夫だと思っていたのですが、聴者に気づかせるためにあえて音声合成で喋るのが必要という指摘をいただけたのはなるほどと思いました。
– Pekoeのセミナーに参加して聴覚障がいにもいろいろ種類があることを知った
木下:
Pekoeのお客様から要望のほかに感謝の声も多くいただき、私はPekoeの仕事に関わってよかったと思っています。Pekoeの開発に関わってよかったということありますか。
木村:
2つあります。
ひとつは聴覚障がい者のことを知ることができたこと。いままでは聴覚障がい者という言葉一括りでみんな同じような人って捉えていました。Pekoeのセミナー(※2)に参加して、生まれつきのろう者の方や中途失聴の方など聴覚障がいにもいろいろ種類があり、困りごとも各々違う。お客様からの要望もその障がいの違いからそれぞれ違うこともわかるようになりました。
もうひとつは自分が作ったもので聴覚障がい者と聴者が一緒に仕事がしやすくなったことを直接感じることができたことです。
(※2)Pekoeのセミナー:「聴覚障がいを知る、学ぶ、考える。」
真野:
Pekoeはファンがついてくれているのがいいなと思っています。毎日起動してくれている話を聞いて、ないと困るアプリになっているのだなと感じています。要望や厳しい意見が直接届くのもいいですね。
– 「ろうあ体験」から反応が見えない、できないことに気づいた
木下:
厳しい意見も届くのですか?
真野:
はい、届きます。それは期待されていると受け取っています。
エンジニアとエンドユーザーは一緒ではないという考えは一般的にありますが、Pekoeはそれが結構強い。我々は聴覚障がい者の体験はできるけど聞こえない当事者にはなれないところです。求められている機能とか、使いやすさの感覚は当事者とは違うことを気づかせてくれます。
木下:
聞こえない当事者になれないことについては、スピーカーの音声を消して、会話もミュートにして会議に参加する「ろうあ体験」をしてもらったことありましたがどうでしたか?
真野:
静かというか会議参加者の反応がわからないことに困りました。反応がわからないから反応できない。自分がわかっているのか、わかっていないことがあるのかも伝えられないもやもやがありました。
木下:
その思いからPekoeのリアクション機能が搭載されたのですね。
聴覚障がい者と聴者の溝をなくしたい
木下:
今後Pekoeでやりたいことがあったら聞かせてください。
真野:
聴覚障がい者向けサービスといえば「Pekoe」というふうに認知されるとやっている甲斐はあると思います。
木村:
お客様にお話を伺っているうちに、文字起こし以外にも課題があると思いました。文字起こしがきちんと出来るようになっても聴覚障がい者と聴者の壁、溝が埋まらない気がしています。すぐには解決できないと思いますが、その溝を埋める解決方法を日々の活動やお客様との対話の中でから見つけ出し、そこを手助けできるPekoeを作れたらいいなと考えています。
木下:
会議の参加者のひとりでも聴覚障がいのことを理解してくれていると会議に参加しやすかったし、逆に理解されていないと溝を感じて会議に参加しづらかったです。
Pekoeを通して会議参加者が聴覚障がいのことを理解してくれるようになり、Pekoeが溝を埋めてくれていると感じています。これからPekoeがどう成長していくのか非常に楽しみです。本日は素敵なお話ありがとうございました。
Pekoeは無料でお試しいただけます。
ぜひみなさまもトライアルをご検討ください。
Pekoe公式ホームページ
トライアル申し込み
※この記事では、聴覚障害ではなく聴覚障がい表記に統一しています。