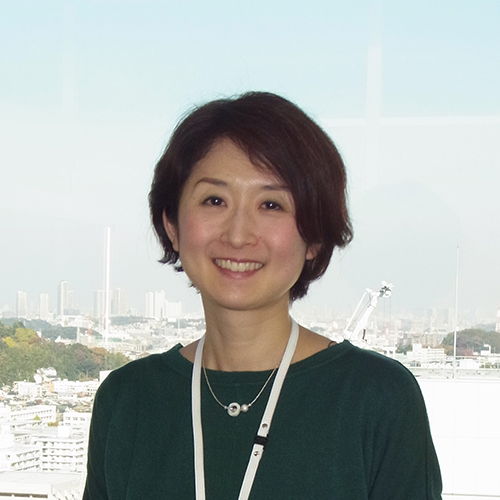バリアフリーの補助金と申請方法は?リフォーム対象や4つの注意点もわかりやすく解説!

障害者や高齢者が自宅で快適に過ごすためのバリアフリーリフォームは、国や自治体から補助金が出たり、税金が控除されることもあります。
これからバリアフリー工事をしようとお考えの方のなかには、
「バリアフリー工事ではどのような補助金が出るのか?」
「補助金をもらうにはどのような申請をすればいいのか?」
などの疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか。
そこで本記事ではバリアフリー補助金の仕組みと申請方法を詳しくご紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
目次
バリアフリーリフォームとは?
バリアフリーリフォームの目的は、住む人が安全で快適に過ごせる環境をつくることです。
怪我や病気などが理由で今すぐ工事が必要という方もいれば、先々の暮らしを考えてバリアフリー化を検討する方もいます。
バリアフリーリフォームをすることで、家庭内の事故のリスクを抑えられます。
日常生活で体への負担を減らし、長く健康を維持するためにも、早めに住環境を見直し、安全に暮らせる環境を整えることが必要です。
バリアフリーにはどんなものがある?
「バリアフリー」とは、もともとは建築用語で「バリア(障壁)」「フリー(除く)」を表し、障壁となるものを取り除き、生活しやすくするという意味です。
建築物の入り口や道路の段差などの物理的なバリアや、高齢者・障害者などの社会参加を困難にしている社会的・制度的・心理的なバリアなど、私たちの身の回りには多くの障壁が存在します。
バリアフリーに関係する補助金について
これからバリアフリーリフォームをお考えの方は、以下の補助金を活用するのがおすすめです。
- 介護保険の高齢者住宅改修費用助成制度
- 自治体の補助金
- バリアフリー改修に関する特例措置
- 所得税の特別控除
- 固定資産税の特別控除
国の補助金だけでなく、自治体独自の補助金や税金の控除もあるので、内容を確認してお得にリフォームできるよう参考にしてみてください。
介護保険の高齢者住宅改修費用助成制度
高齢者住宅改修費用助成制度は、在宅で介護を受けるため、自宅をバリアフリー化した場合に、その一部を助成してもらえる制度です。
介護保険から支給される住宅改修費の補助金は、最大20万円分が適用されます。
限度額の範囲内であれば、複数回の申請も可能で、 要介護状態区分が重くなった場合や、転居の際には再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
参考記事:介護保険における住宅改修|厚生労働省
自治体の補助金
介護保険適用の住宅改修は、基本的に20万円を超えると介護保険での支給対象にならなくなります。
しかし、自治体によっては介護リフォームの住宅改修補助制度があるので、上限を超えてしまっても、自治体の補助金が受けられるかもしれません。
住宅改修補助制度が受けられる自治体では、住宅改修費に加えて利用できるので、介護のための住宅改修の負担を最小限に抑えることが可能です。
例えば、東京都でバリアフリーリフォームをする際には、「高齢社会対策区市町村包括補助事業」を活用できます。
住宅改修の予防給付として、1世帯あたり20万円の補助があります。
自治体によって補助金の内容は異なるので、お住まいの行政窓口でご確認ください。
参考記事:東京都福祉局「住宅改善事業(バリアフリー化等)区市町村別事業概要一覧」
バリアフリー改修に関する特例措置
バリアフリー改修をした建物に関して、贈与税や登録免許税、不動産取得税などの税金の特例措置があります。
工事資金の贈与を受けた場合には非課税枠が設けられたり、個人が宅地建物取引業者から改修済みの住宅を取得した場合には登録免許税が軽減されます。
宅地建物取引業者に対し、バリアフリー改修を対象とした不動産取得税が軽減される措置もあるので、事前に税務署などで確認をしておくとよいでしょう。
所得税の特別控除
耐震改修や省エネ改修などの特定のリフォームをする際に受けられる減税制度があり、控除を受けることで資金の一部が戻ってくる可能性があります。
自己資金でリフォームをおこなった場合、その年の所得税から控除を受けられます。
バリアフリーリフォームの最大控除額は、借入金の有無に関わらない投資型で20万円、償還期間が5年以上の借入金によるローン型の控除額は25万円です。
固定資産税の特別控除
リフォームでは、固定資産税を1/3減額できるケースがあります。
減税期間は1年間で、工事完了後3ヵ月以内に申告をしなければいけません。
家屋面積の制限や減税の併用ができるものとできないものがあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
参考記事:住宅リフォームにおける減税制度について|国土交通省
バリアフリーリフォームの補助金の申請方法

介護保険を活用したバリアフリーリフォームの補助金の申請は以下の手順でおこないます。
- 住宅改修についてケアマネジャーに相談
- 申請書類または書類の一部提出・確認
- 施工・完成
- 住宅改修費の支給申請・決定
一般的に、補助金の申請は施工前に書類を提出しなければいけないので、スケジュール管理が大切です。
また、給付方法は償還払いのため、一度リフォーム会社に費用の全額を支払い、後日自治体から補助金の給付を受ける流れとなります。
バリアフリーリフォームの補助金は最大いくら出る?
介護保険におけるバリアフリーリフォームの補助金は、支給限度基準額20万円の9割である18万円が上限となります。
ほかの介護保険サービスの支給限度額に加算されないため、すでにほかの介護保険サービスで給付を受けている方も、限度額を気にせずに申請できるのが特徴です。
自治体ごとに補助金制度がある地域もあるので、支給額を把握しておくことで金銭的な負担が軽減されます。
バリアフリーリフォームの補助金の支給条件
介護保険制度を利用してバリアフリーリフォームの補助金を受給するためには、3つの支給条件を満たす必要があります。
- 要介護認定されている介護保険の被保険者であること
補助金を受給するためには、介護保険の被保険者である40歳以上で、要介護認定で「要支援1〜2」もしくは「要介護1〜5」のいずれかに認定されていることが必要です。
- 対象の住宅が被保険者の住所と一致すること
補助金の対象となる住宅は、「介護保険被保険者証」に記載されている住所の住宅です。
そのうえで、被保険者が実際にその住宅を利用していることが条件になります。
- 利用者が福祉施設や病院に入っていないこと
被保険者が福祉施設に入所していたり、病院に入院している場合は、被保険者が自宅を利用しているとは判断できないので、補助金支給の対象外になってしまいます。
3つの条件をすべてを満たしていないと対象外になってしまうので、事前にご確認ください。
バリアフリー住宅を新築する場合も補助金は出る?
バリアフリー住宅を新築する場合も、国や地方自治体から補助金が出ることがあります。
市町村によって内容や条件は異なりますが、「高齢者住宅支援制度」や「高齢者福祉住宅整備事業」などで定められていることが多いです。
新築を手がける工事業者のなかには、補助金や支援制度の知識をもっていて、金銭的な負担がなるべくかからないような提案をしてくれるところもあります。
補助金や支援制度を受けるときには、ほとんどの場合、細かい申請書類やバリアフリー住宅の写真などが必要です。
そのため、新築する際には、バリアフリー住宅の施工実績がある業者に依頼することをおすすめします。
介護リフォーム補助金は何回も申請できる?
介護リフォーム補助金の支給は、原則一人の被保険者につき1回のみです。
ただし、1回の申請が限度額に満たない場合は、複数回に分けて申請ができます。
しかし、要介護度の等級が3段階以上上がったり、転居した場合には、再度限度額まで受給することができます。
また、ひとつの住宅に支給対象となる被保険者が複数名いる場合は、重複工事でなければそれぞれ1回ずつの補助金申請が可能です。
バリアフリーリフォームの対象になる工事は?
バリアフリーリフォームは、すべての工事が補助金の対象になるわけではありません。
具体的な対象工事は、以下の6つです。
- 手すりの設置
- 床材の変更や滑り止めの設置
- 段差の解消
- ドアの変更・取り換え
- 設備の取り換え
- 間取りの変更
これからリフォームを検討している方はぜひ参考にしてください。
手すりの設置
高齢者や歩くのに困難な障害をもつ方にとって、転倒防止・立ち座りの手助けとなる手すりはなくてはならないものです。
玄関や階段、トイレや風呂などの段差部分、立ち座りするスペースに手すりがあれば、家の中の移動がしやすく、立ち上がる動作も楽になります。
手すりの設置は、使用者の背丈や動きに合わせて取り付けることがポイントです。
手すりの形状や材質、太さ、位置に配慮し、使うときに手が届くか、しっかり握れるかを確認して選びましょう。
床材の変更や滑り止めの設置
床材の状態や素材によっては転倒しやすい場合があるので、滑りやすい場所は床材の変更や滑り止めを設置するリフォームが必要です。
衝撃を和らげるクッション性のある床材に変えることで、室内の安全性が高まり、転倒のリスクを減らせます。
キッチンやトイレなどの水で濡れやすい場所は、掃除のしやすさも大切です。
床材によって価格は大きく変わるので、リビングや寝室など広い範囲のリフォームを検討している方は、あらかじめ見積もりをとってから検討してみるといいでしょう。
段差の解消
足腰が弱ってくると、部屋と廊下のわずかな段差も転倒の原因です。
段差にスロープを設置したり、低いほうの床の高さを上げると段差の解消になります。
特に車椅子生活の方にとって段差の解消は不可欠ですが、段差が大きい場所ではスロープが急勾配にならないようにしないと、スピードが制御できなくなってしまって危険です。
大きな怪我や後遺症につながる可能性もあるため、段差の解消のリフォームでは、専門業者やケアマネージャーなどに相談して計画を立てるとよいでしょう。
ドアの変更・取り換え
筋力が弱まったり手先が不自由な方は、扉やドアの変更・取り換え工事が必要になることもあります。
よくあるバリアフリーリフォームでは、介護者自身でドアの開け閉めができるように、引き戸・開き戸へ、または引き戸・開き戸からアコーディオンカーテンへ変更する工事が多いです。
ドアを変更するだけで、移動がスムーズになり体への負担も減らせます。
ドアの形状が変えられない場合でも、ドアノブを握りやすいものにする、ドアの材質を軽いものにするなどの開閉をスムーズにする方法があります。
設備の取り換え
トイレやキッチン、お風呂などの設備を取り換えることでも、安全性や利便性が高まります。
例えば、古いお風呂の場合、タイル貼りの床、高さがある浴槽など身体が不自由な方は入浴するにも一苦労です。
浴室内は水で濡れていて滑りやすく、家庭内では事故が起こりやすい場所でもあります。
低めの高さの浴槽に変更したり、さらに暖房設備付きの浴室に変更すれば、ヒートショックのリスクも軽減でき、入浴時の体への負担も大きく下げられます。
築年数の長い住宅によくある和式便所は、高齢者の方には使いにくく不便なので、座りやすい洋式便座に便器を変えるリフォームも効果的です。
トイレはタンクレスにすることで使える空間が広くなり、立ち座りの動作がしやすくなったり、介助する際にもサポートしやすくなります。
間取りの変更
高額な費用がかかるリフォームですが、住居の間取りの変更も効果的な工事です。
廊下を広くする、車椅子でも使いやすいようにトイレやリビングを設計し直すなど、暮らしやすいようにリフォームする方も多くいます。
間取りをどれだけ変更できるかは、住宅の構造や柱の位置によって大きく異なりますが、生活導線を可能な限りシンプルにして、余裕のあるスペースを設けることがポイントです。
例えば2階建て以上の住宅の場合は、1階に生活空間をまとめれば、階段の上り下りの苦労がなくなり、少ない動作での生活ができるようになります。
バリアフリーリフォームの前に注意したい4つのポイント

これからバリアフリーリフォームする方は、以下の4つのポイントを事前にご確認ください。
- 早めに計画する
- 補助金や制度は事前に調べる
- バリアフリーの知識がある業者に依頼する
- 申請時期・タイミングに注意する
詳しい内容を把握して、早めに行動することが大切です。
早めに計画する
バリアフリーリフォームでは、スケジューリングが大切です。
必要に迫られてリフォームをせざるを得ない状況もありますが、焦って計画すると失敗するリスクが上がってしまいます。
先々を見据えて、使いやすい住環境にするためには、早めに計画を立てることをおすすめします。
少しでも生活に不自由を感じるようであれば、バリアフリーを進めて安全な自宅にすることは、暮らす方の自立性や体力の維持にもつながります。
補助金や制度は事前に調べる
費用面が心配でリフォームの計画が進まない方は、補助金制度、リフォームローンの活用も検討しましょう。
介護保険を使う場合はケアマネージャーへの相談や、工事前の申請が必要です。
自治体の補助金も、契約や着工前の申請が条件となるものが多く、手続きを忘れると補助金が受け取れなくなってしまいます。
自治体の支援制度については、リフォーム業者が指定されているケースもあるため、業者を決める前に自治体のホームページや窓口で確認するといいでしょう。
バリアフリーの知識がある業者に依頼する
どのようなリフォームが必要なのか、どのタイミングで工事を始めるのかは、ケアマネージャーや主治医、建築士などの専門知識がある方に相談するのがいいでしょう。
業者を選ぶ際には、バリアフリーの施工実績や、福祉住環境コーディネーターなどのバリアフリーの知識を持つ方が在籍しているか確認することをおすすめします。
バリアフリーリフォームは通常のリフォーム以上に、安全に暮らせるか、住む方や介助者の負担を減らせるかという視点が欠かせません。
実績のある業者であれば的確なアドバイスがもらえて、補助金について教えてもらえることもあります。
申請時期・タイミングに注意する
リフォーム補助金の多くは、税金で運営されていることもあり、予算や期間が限られています。
利用を検討する際には、申請時期やタイミングにご注意ください。
補助金や助成金制度は、ほとんどの場合、着工前に申請しなくてはいけません。
工事を開始してしまってからの申請や、工事完了後では、原則として受理されないことが多いので事前の確認が大切です。
また「◯月◯日までに工事を完了させること」などの条件付きである場合も多いため、工事日の調整もする必要があります。
まとめ
今回の記事では、バリアフリーリフォームの詳しい内容を解説しました。
バリアフリー工事では、介護保険をはじめ多くの補助金を使ったり、税金の控除を受けることができます。
どのような工事でも補助金を活用できるわけではなく、対象となる工事が限られていたり、申請方法や時期にも注意が必要です。
これからバリアフリーリフォームをお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。